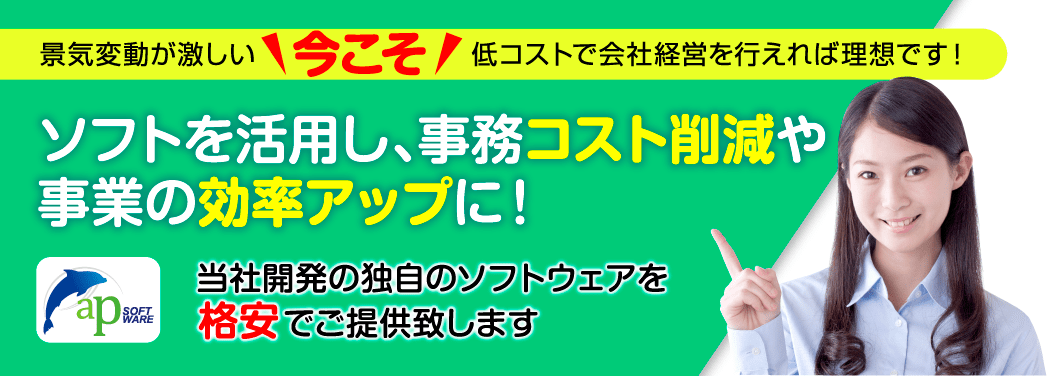お役立ち情報
内容証明の郵便料金は?文書の作成方法から出し方まで徹底解説!

「内容証明を出したいけれど、正確な郵便料金がわからない」「手続きが複雑そうで、なかなか踏み出せずにいる」と悩む方も多いでしょう。
内容証明は、金銭や契約に関するトラブルに直面したときに、自分の権利を守るための重要な手段です。
本記事では、内容証明郵便の正確な料金をはじめ、法的効力や正確な出し方の手順まで、トラブルを解決する方法を徹底解説します。
内容証明の郵便料金

内容証明は、通常の郵便よりも料金体系が複雑です。基本料金に加えて、書留代や内容証明の加算料金、各種オプション代がかかるため、総額がいくらになるか事前に確認しましょう。
1.内容証明の料金
一般の内容証明の料金は次の通りです。
| 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚以上 |
| 480円 | 770円 | 1,060円 | 1,350円 | 1,640円 |
内容証明の料金は、原則として複数の切手を組み合わせて支払います。
ただし、切手は封筒に貼らず、料金総額分の切手を郵便局の窓口に持参して、そのまま提出してください。
引用元:内容証明 ご利用の条件等「内容証明の加算料金(一般の内容証明の場合)」
2.郵便物の料金
定形・定形外郵便物の料金は次の通りです。
| 種類 | 重量 | 料金 |
| 定型郵便物 | 50g以内 | 110円 |
| 定形外郵便物(規格内) |
50g以内 | 140円 |
| 100g以内 | 180円 | |
| 150g以内 | 270円 | |
| 250g以内 | 320円 |
定形郵便物の料金は、2024年10月1日に改定されました。料金を間違えると郵便物が戻ってくるなど、手続きが遅れる原因になりますので、最新の料金を必ず確認しましょう。
3.一般書留の料金
一般書留の料金は次の通りです。
| 損害要償額が10万円までのもの | 480円 |
| 損害要償額が10万円を超えるもの | 5万円またはその端数ごとに23円を加算 |
一般書留は、郵便受けへ投函されるのではなく、受取人本人または同居人に直接手渡しされます。これにより、内容証明を確実に相手に交付し受領の記録を残せます。
4.配達証明の料金
配達証明の料金は次の通りです。
| 差出時 | 350円 |
| 差出後 | 480円 |
配達証明は、郵便物を差し出す際に窓口で同時に請求するのが一般的です。
万が一、請求を忘れてしまった場合でも、一般書留として差し出してから1年以内であれば、差出郵便局に受領証を提示することで、あとから配達証明を請求できます。
引用元:内容証明 ご利用の条件等「その他の主なオプションサービスの加算料金」
内容証明の郵便料金例
一般的な内容証明の郵便料金は次の通りです。
| 謄本(1枚) | 480円 |
| 定形郵便物(50g以内) | 110円 |
| 一般書留:480円 | 480円 |
| 配達証明(差出時) | 350円 |
| 合計 | 1,420円 |
内容証明の料金は、内容文書の枚数(郵便局に提出する謄本の枚数)が増えると、加算料金も高くなるため注意が必要です。
e内容証明(電子内容証明)の料金
e内容証明(電子内容証明)は、日本郵便が提供するオンラインサービスです。
作成した文書データをインターネットでアップロードするだけで、印刷・照合・封入・発送といった窓口での煩雑な手続きをすべて日本郵便が代行してくれます。
e内容証明の料金は次の通りです。
| 郵便料金 | 110円 | |
| 電子郵便料金 | 電子内容証明文書1枚目 | 19円 |
| 電子内容証明文書2枚目以降1枚ごとに(5枚まで) | 6円 | |
| 内容証明料金 | 電子内容証明文書1枚目 | 382円 |
| 電子内容証明文書2枚目以降1枚ごとに(5枚まで) | 360円 | |
| 同文内容証明(2通目以降1枚目) | 210円 | |
| 同文内容証明(2通目以降2枚目以降1枚ごとに) | 210円 | |
| 謄本送付料金 | 通常送付 | 304円 |
| 一括送付(受取人数100人まで) | 503円 | |
| 一般書留料金 | 480円 | |
e内容証明でも、通常の郵便と同様に配達証明や速達などのオプションを利用できます。
内容証明とは?

内容証明とは、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」という事実を、郵便局(日本郵便)が公的に証明してくれる一般書留郵便の一種です。この証明書は、後に裁判や交渉になった際の重要な証拠となります。
ただし、内容証明郵便自体には、相手に何かを強制する「法的拘束力」は原則としてありません。そのため、請求に応じるかどうかは相手の判断によることを覚えておきましょう。
内容証明と配達証明の違い
配達証明とは、一般書留郵便に付加するオプションで、「郵便物がいつ、相手に配達されたか」という事実を郵便局が証明するサービスです。
内容証明と配達証明は混同されやすいため、それぞれの証明の違いを明確に把握しておきましょう。
| 内容証明 | 配達証明 | |
| 証明する対象 | 文書の内容 | 配達の事実 |
| 目的 | 公的な証拠作り | 到達の証明 |
| 単独利用 | 可能(ただし、必ず一般書留で送る必要がある) | 内容証明とセット、または一般書留とセットで利用する |
| 法的効力 | 一部で法的な効果を持つことがある | 法的効力は持たないが、内容証明の効力を強める |
内容証明を送る際は、配達証明をオプションで追加し、セットで利用するのが一般的です。
内容証明の法的目的

内容証明の本質的な目的は、法的な証拠を確保することです。具体的にどのような目的があるのか解説します。
水掛け論を回避する
普通の郵便やメールでは、「届いていない」「そんな内容は書いていなかった」と相手に言い逃れされるリスクがあります。
これに対し、内容証明を利用すれば、「いつ、誰に、どんな内容を送ったか」という事実を郵便局が公的に証明してくれるため、水掛け論を確実に回避することが可能です。
日付を公的に証明する
内容証明に配達証明を併用することで、文書が相手に「いつ到達したか」という日付を公的に証明できます。
この到達日時の記録は、クーリングオフの期限や契約解除の効力発生日など、法律で期間が定められている重要な意思表示の有効性を証明するために必要です。
心理的プレッシャーを与える
内容証明は、「裁判も辞さない」という差出人の強い意志を相手に伝えるための最終通告としての役割を果たします。
そのため、これまで通知を無視していた相手でも、内容証明が届いたことで事態の重大性を認識し、交渉や支払いに応じるきっかけになるという心理的な効果が期待できるでしょう。
権利の消滅を防ぐ
内容証明は、借金や損害賠償請求権などの消滅時効が成立するのを防ぐ目的でも利用されます。
時効成立前に内容証明を送付し「催告(さいこく)」を行うことで、時効の完成が一時的に(6ヶ月間)猶予されます。
内容証明の作成方法

内容証明の書き方は、文書に法的効力を持たせるため、非常に細かく定められています。ここでは、正確な謄本を作成するためのポイントを解説します。
字数・行数の制限
謄本を作成する際は、次の字数・行数の制限を守りましょう。
| 区別 | 字数・行数の制限 |
| 縦書きの場合 |
|
| 横書きの場合 |
|
句読点やカッコも1文字としてカウントします。
必須記載事項
謄本には、次の事項を必ず記載しましょう。
- 差出人の住所・氏名
- 受取人の住所・氏名
文書内の住所・氏名は、封筒の記載と一字一句完全に一致させなければなりません。
同一文書3通
内容証明を送る際は、完全に同一の内容の文書を合計3通用意する必要があります。
内訳は次の通りです。
- 正本:受取人へ送付するもの
- 謄本:差出人が控えとして保管するもの
- 謄本:郵便局が保管するもの
パソコンで3枚プリントアウトするか、手書きの場合は2枚コピーを取るなどして、3通すべてが同じ内容であることを確認してください。
内容証明の出し方

内容証明郵便は、法的トラブルを回避・解決する強力な証拠となるため、手順を正確に守ることが大切です。ここでは、内容証明の出し方について解説します。
差出可能な郵便局を確認する
内容証明は、集配業務を行う大きな郵便局、または日本郵便が指定した一部の郵便局の窓口でしか取り扱いができません。
事前に電話や日本郵便のウェブサイトで、差出予定の郵便局が対応しているかを確認しましょう。
必要書類と印鑑を準備する
内容証明の提出に必要なものは次の4点です。
- 同一文書3通(受取人への正本1通、差出人・郵便局用の謄本2通)
- 封筒1通
- 差出人の印鑑
- 郵便料金(現金または切手)
内容文書以外の図面、写真、返信用封筒などは一切同封できないのでご注意ください。
窓口で手続きを行う
内容証明の手続きは、準備した書類一式と印鑑を持って窓口で行います。
手続きの手順は次の通りです。
- 局員が3通の文書すべてを回収し、字数や記載内容、印鑑(契印)の有無など、形式規定を細かくチェックする。
- 不備が見つかった場合は、差出人の印鑑を用いて訂正する。
- チェック後、局員の立ち会いのもとで正本を封筒に入れ、封をする。
3通すべての文書に郵便局の「内容証明」認証印が押されて、手続きが完了します。
内容証明を送る際の注意点

内容証明は交渉や訴訟を有利に進めるための重要な証拠です。ここでは、内容証明を送る際の注意点について解説します。
配達証明を併用する
内容証明郵便を差し出す際は、配達証明を併用しましょう。
配達証明をつけることで、「その文書がいつ、相手に確実に届いたか」という事実も公的に証明されます。
多くの法的な効力が「相手に文書が到達した日」に発生するため、配達日と受取人を証明することが重要です。
客観的な事実と法的根拠を記載する
内容証明の文書には、感情的な言葉や攻撃的な表現を含めないよう注意が必要です。感情的な文章は、かえって相手の反発を招き、あとから交渉や訴訟を難しくする原因になります。
文書を作成する際は、次の2点に注意しましょう。
- 客観的な事実のみを記載する
- 行為の法的根拠を明確にする
これらを守ることで、内容証明が単なる個人的な主張ではなく、裁判所でも通用する確かな証拠となります。
要求内容と期限を明確にする
内容証明では、曖昧な表現を避け、相手に求める具体的な行動を明確に指示することが重要です。要求が曖昧だと、相手の対応の遅れや未対応につながる可能性があります。
文書には、次の2点を必ず記載しましょう。
- 具体的な要求内容(例:具体的な金額、品物、行為など)
- 明確な期限設定(相手が行動を起こす期限)
これらのポイントを守ることで、相手に具体的な行動を促す圧力となり、のちの裁判や交渉の場で有力な証拠として活用できます。
未入金の回収には「ペイド督促代行」がおすすめ

督促業務は、電話や文書作成・状況管理など、時間と労力がかかる作業であり、人手が限られている場合は本業に大きな負担をかけます。
この負担を軽減したい企業には、「ペイド督促代行」がおすすめです。
請求書作成から発送、入金チェック、督促業務までがワンパッケージになっているため、督促業務の負担を大幅に軽減できます。
「ペイド督促代行」の費用明細は次の通りです。
| 月額料金 (1事業所あたり) |
6,000円 |
| 子アカウント料金 (複数ユーザーで利用時) |
1日300円(日割) |
| 成功報酬(入金時のみ) | 1,000円 |
入金管理や督促業務をシステム化することで、時間や人的コストを大幅に削減し、本来の業務に集中できるようになります。
まとめ

内容証明の郵便料金は、通常の郵便に比べて料金体系が複雑です。
内容証明の枚数や郵便物の重さ、オプションによって料金が異なります。内容証明を送る際は、事前に日本郵便のウェブサイトや窓口で、正確な料金を確認しましょう。
督促業務を効率化したい場合は「ペイド督促代行」がおすすめです。請求書作成から入金確認・督促業務までを一括してシステム化することで、業務負担を大きく軽減できます。
【Q&A】
- 内容証明とは?
内容証明とは、送った文書の内容を郵便局が証明してくれるサービスです。
- 内容証明の郵便料金は?
内容証明の郵便料金は次の要素で構成されます。
- 内容証明の料金
- 郵便物の料金
- 一般書留の料金
- 配達証明の料金
- その他オプション
内容証明を送る際は、事前に日本郵便のウェブサイトや窓口で、正確な料金を確認しましょう。